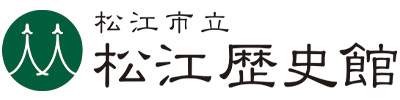第34回 転勤の時期に思い出すこと
今年の春は、例年に比べ、暖かくなるのが遅いように思っていましたが、10日過ぎから順調に気温が上昇してきました。おかげで、桜は長持ちしたように思います。これからは、牡丹、なんじゃもんじゃと花が続きます。畑では、エンドウやソラマメ、ニンニク、タマネギが順調ですし、ジャガイモも芽が出てきました。今年も、まずは順調なスタートが切れました。
4月は人事異動、転勤などで新たな生活が始まる時期です。私は1971年に自治省に入り、2000年に退職しましたが、その約30年間に、東京と地方とを往復転勤しました。当時の一般的な昇任パターンは次のようになっていました。先ず入省後3か月は本省での研修、その後、県に職員として出向、1~2年後に本省に係長級(主査)として復帰、入省5年後に県の課長(市では部長)に、30代前半に本省の課長補佐に、30代後半に県の部長(市では副市長)に、40代前半に本省の課長級(企画官)に、40代後半に本省の課長に、50代の初め審議官(早い人では退職して外郭団体の役員)に、その後限られた人が局長そして次官になります。
地方に出向した場合、当然のことながら自分一人で飛び込むわけですから、大変だろうと思われるかもしれません。事実、これを称して「落下傘」と言われることがあります。しかし、心配には及びません。県や市の職員には大変親切にしていただきました。最も、人権感覚が鈍いとか長期観光滞在者とかいわれ、批判されることもありましたが・・・。結局、本省の持っている権限や財源を考えれば、その人を県、市と本省をつなぐパイプとしたいという考えもあるのでしょう。将来、本省で出世をしてもらい、自分たちの県や市のことを大事にしてもらうために、その出向してきた人を大事にしてくれるのでしょう。
このように、仕事や人間関係で悩むことは全くありませんでしたが、同じ県に出向している先輩との関係で苦悶したことがあります。自治省では先輩には絶対服従というのが不文律でした。昭和51年に和歌山県の土地利用対策課長の辞令をいただきました。当時、私は群馬県の課長の内示を受けていたのですが、知事が変わり、当面国から課長は出向しないことになり、内示は取り消され、同期の中で一人自治省にとどまっていました。
当時の事務次官は昔和歌山県の地方課長を務めた方で、和歌山県に対する思い入れが強い方でした。一方、私が赴任したころの和歌山県は地方自治法が施行されていない県だと評判が立っていました。経験の少ない者が課長を務めるには少々骨の折れるところでした。
次官が課長を務められてから、3代自治省からの出向者が続いたのですが、その後、総務部長のポストに替わり、地方課長は以来地元の人が占めてきました。次官は何とか地方課長のポストを復活させたいと考えておられ、一人残っていた私に和歌山行きの辞令が出たのです。2年ほどほかの課長を務め、評判が良ければ地方課長にしてもらうようにお願いするという約束でした。しかし、2年たってもそうした話になりませんでしたので、これは私の評判がよくないせいだと思いつつも、自治省の先輩の総務部長に相談したのですが、「そんな約束は聞いていない」というつれない答えでした。それ以上お願いしても努力していただけそうもありません。人の気持ちのわからない人だ、人情の薄い人だと思いました。
ところが、どこでその話を聞きつけたのか、大蔵省から出向していた財政課長が「マッちゃん、知事に話してみようか」と言ってくれたのです。ほどなく知事から呼ばれ、「君を地方課長にしようと思うがどうか」と言われましたので、「そのポストは地元の人たちが守ってきたものですが、それを手放すことができるでしょうか」などと失礼なことを言ってしまいました。知事は「イエスかノーか言えばいい」と叱られました。知事にとっては地元の職員から批判されることがわかっていながら決断していただき、感謝に堪えません。人の情けのありがたさを感じた瞬間でした。
それにしても、大蔵省の財政課長が知事に言えて、先輩の総務部長がどうして知事に言ってくれなかったのか、言えなかったのかです。要するに、知事との関係が裃を着た付き合いでしかなかったから、腹を割ったフランクな付き合いができていなかったからではないかと思っています。人の値打ちとはどういうものか、人を動かすとはどういうことか、仕事を進めるうえで何が必要なのかを痛感しました。人間関係はまじめなだけでは足りない、人生の貴重な経験でした。